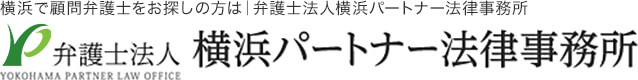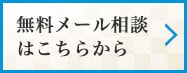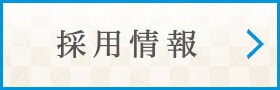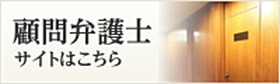カラマーゾフの弁護士
第280号 カラマーゾフの弁護士
「カラマーゾフの兄弟」は、ドストエフスキーの長編小説ですね。金持ちだが、ケチで好色な、どうしようもない父親と、3人兄弟の話です。上の兄は父親似の遊び人、真ん中が理知的で理屈好き、三男の主人公が天使のように気立ての良い人だという設定です。やがて父親が殺されて犯人捜しとともに物語が進んでいくという、とても面白い小説です。さらに、小説内の「大審問官の例え話」も有名です。宗教裁判が盛んにおこなわれていた16世紀のスペインに、イエス・キリスト本人がやってくるという話です。キリストはスペインの大審問官によって、厳しく弾劾されるという話です。キリストは現実の世の中を良くしようとはしませんでした。いずれ「最後の審判」の日がやってくれば、それまでの不正は罰を受け、善い行いをしたものは報いを受けると教えていただけです。現実の世界をよくするためには、「力」が必要なのに、キリストはそれを求めようともしなかった、というのが、大審問官のキリスト批判です。最後の審判で全てが正しいことになるといっても、それまでになされた不正や、辛い目にあった人の悲しみが、消えてしまうわけではない。ドストエフスキー大先生は、親に虐待された娘の例を挙げていました。自分の親から酷い仕打ちを受け、逃げ場がない中で苦しんでいる。(こういう「虐げられた人々」を書くの、ドストエフスキー大先生、本当にうまいんですよね。)
それなのに、キリストは、「力」を得て不正と戦おうとせずに、「いずれ「最後の審判」でチャラになるから良いでしょう」と言っているだけというわけです。この「大審問官の批判」は、裁判制度や弁護士の役割とも関連することだなと、ハッと気が付いたのです。(なんだそりゃ。。。)法律や裁判の制度というのは、基本的に過去に起こった事件について、裁きを与えます。「思い出の 事件を裁く 最高裁」なんて川柳がありましたが、事件が起こってから、10年以上も経って初めて、「正義が実現」されたなんてことはざらです。冤罪事件で苦しんでいた人が、たとえ最高裁で無罪となっても、それまでの苦しみが消えるわけではないのです。まさに、大審問官のキリストに対する批判が当てはまる制度といえます。
弁護士の仕事の場合は、さらに問題があります。弁護士は依頼者のために活動するのが仕事です。ドストエフスキー大先生は、弁護士が嫌いだったようで、カラマーゾフの中でかなり攻撃していました。先ほどの、親に虐待されていた娘の話で、弁護士の仕事は虐待していた親の方を弁護することだというんですね。「これはよくある家族内の事件です。父親が自分の娘を躾けただけです。これを犯罪だというのは、現代の恥辱です」みたいに弁護するんだそうです。現代日本でも、本当にこういう感じのことを言う弁護士が居そうです。。。
そんな風に虐待する親を弁護するかどうかはともかく、こういう事件を防ぐためには、弁護士は全く無力です。弁護士制度も、裁判制度の一環ですから、「事件が起こってから初めて動き出す」のが原則なわけです。そんな弁護士の在り方に満足できないで、大審問官のように、現実の不正と戦うために「力」を付けようとする弁護士も沢山います。政治家になったり、社会活動家となったりして、不正と戦おうとするわけです。しかし、「力」を得て活動した大審問官は、「異端審問」「宗教裁判」などを行い、かえって世の中を悪くしたようにも思えます。積極的に活動する弁護士達が、世の中を良くしてくれればと、カラマーゾフの弁護士として祈っているのです。
弁護士より一言
先日、大学生の娘が私に「1つ68円の大特価だった!」と言って、ジャンボアイスモナカを買ってきてくれたんです。喜んでいたら、妻にはハーゲンダッツの新作を渡してます。「僻んではいけない。何か意味があるはずだ」と考えて理由を聞いたら、無邪気に答えました。「ママは質重視だけど、パパは量でしょう!」罪がないジャンボアイスモナカは美味しく食べましたが、「最後の審判のときには、ハーゲンダッツの新作を食べるぞ!」と心に誓ったのでした。
(2020年11月2日 大山滋郎)